
「工務店のビジネスモデルそのもの」が試される時代へ
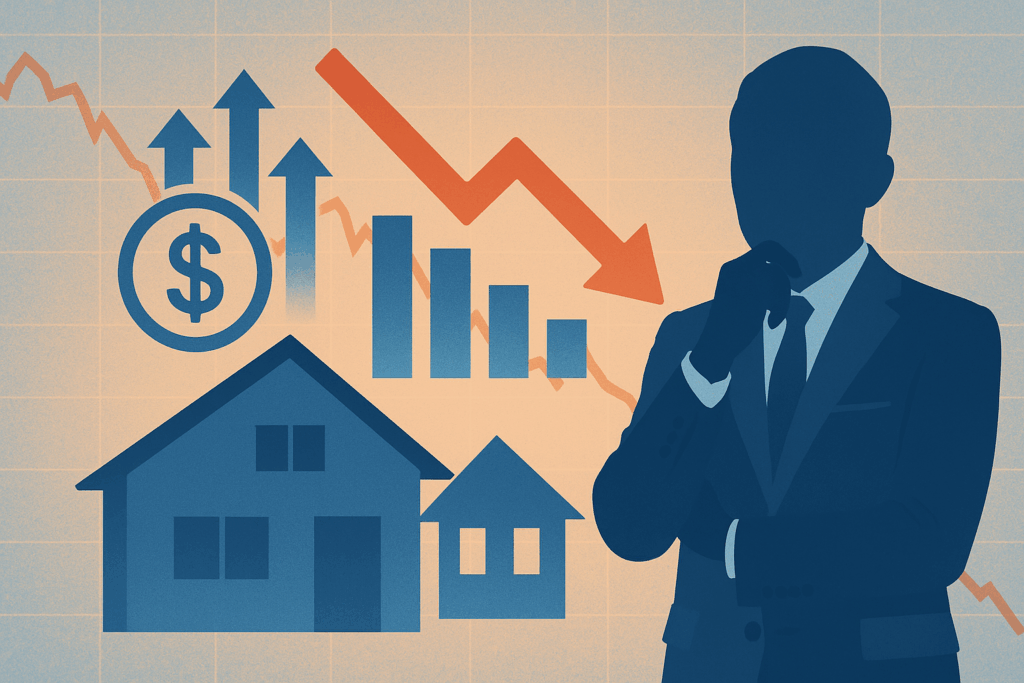
原価インフレと需要デフレがもたらす、二重苦の構造リスク
新築住宅の需要は伸び悩み、供給は一部で過剰。
一方で、建材価格や人件費は年々上昇し続けています。
現場からはこうした声が聞こえてきます。
「契約まではスムーズに進むが、利益が残らない」
「坪単価は上げられず、資材費と人件費が食ってしまう」
「500万円以上の値引き販売が当たり前になってきた」
こうした経営環境の変化において、特に注視すべきは
「設計時点で既に利益が出ない構造が増えている」ということです。
「インフレ」と「デフレ」が同時に起きている矛盾
住宅業界の足元では、インフレとデフレの矛盾が並行して進行しています。
・材料費、人件費、輸送コストなど
→ インフレ(コスト増)
・住宅価格、売れ行き、値下げ圧力
→ デフレ(収益減)
かつては想定していなかったこの「逆風の両輪」が、工務店のビジネスモデルに構造的な打撃を与えつつあります。
例えば、2024年の完成在庫平均価格と坪単価の乖離は、全国平均で500万円超。
一部では「建てるほど赤字」という現象も見え隠れしています。
全国平均では見えてこない「地域ごとのバランス崩壊」
表面的には「全国的に建設費が上がっている」ように見えますが、実際には都市圏と地方で需給バランスが大きく異なります。
・都市部:資材調達や人材確保がしやすい一方、販売競争が激化
・地方:販売価格の下落傾向が強く、工務店は“原価割れ”のリスクに直面
いずれにせよ共通しているのは、「従来型のコスト構造では利益を確保しにくくなっている」という点です。
「ビジネスモデルそのもの」に手を入れるフェーズへ
こうした構造的な変化に対応するには、部分的なコストカットや値上げだけでは不十分です。
本質的には、
・設計・積算の見直し(粗利額視点での収支管理)
・人材採用と定着戦略の再構築(若年層に響く打ち出し)
・工期・物流リスクを織り込んだ原価管理モデル
・地域特性に応じた価格戦略とマーケティング導線
といった、経営モデル全体の再設計が求められるフェーズに入っていると言えるでしょう。
最後に
今回の内容は、住宅業界が今直面している「構造的な変化」のほんの一部です。
より詳細に、
-
原価高騰の構造要因
-
人件費上昇の実態と業界内の給与水準変化
-
物流2024年問題が現場にもたらす影響
-
需給バランスの崩壊とその地域差
といったテーマを掘り下げている書籍があります。
――今読むべき、住宅業界の“現実”を知る一冊。
工務店経営に携わる方、地域工務店の未来に課題感を持つ方にとって、
次の一手を考えるうえでのヒントになる内容が詰まっています。
ぜひチェックしてみてください。
